第12回

岐阜県関市の洞戸地区(旧洞戸村)は人口約1700人の中山間地。清流・板取川が南北を貫き、冬は厳しい冷え込みと積雪に見舞われる。35歳のとき、この地域の診療所に夫人と2人の娘と赴任した。その直後、現在は外科医として活躍する長男を授かった。
この春、在任42年を迎える。そのうち、76歳になるまでの41年間は所長として、外来、訪問診療、学校医など住民の健康を一手に担った。「無我夢中だった。気づいたら、この年になってしまった」と笑う。着任直後、「自転車じゃ訪問診療も買い物も難しい」と夫婦で自動車教習所に通った。「家内はだいぶ苦労したと思う。でも、文句を聞いたことはない。一生懸命助けてくれた。ありがたいと思う」としみじみ語る。
住民に慕われる「大丈夫!」の先生

住民から「『大丈夫!』の先生」と慕われている。穏やかで威張らず、飾らない人柄。口癖の「大丈夫!」を聞きたくて、通院する患者も多いという。
「患者さんとの間で大切なのが信頼関係。話をしっかり聞いてあげるだけでも、患者さんは気持ちが楽になる。誰かひとりでもわかってくれる人がいれば、大きな力とやすらぎになる」
岐阜県大垣市で生まれ育った。医師を志したのは、剣道に没頭していた高校3年生のとき。合指症の子供を巧みに手術する医師を紹介したテレビ番組を見て、岐阜大学医学部に進んだ。早い時期から「漠然と医療過疎地で働きたい気持ちがあった」という。
卒業後は研修医として県立多治見病院に勤務し、故・山下弘副病院長(のちに病院長)から薫陶を受けた。「手術がうまく、威厳のある整形外科の先生だった」と懐かしそうに語る。外科医になりたかったが、「田舎で診療したい」と話すと、「腰や足が痛い人ばっかりだぞ。整形外科をやらんでどうするんじゃ」。
そこで志望が決まった。研修後は岐阜大学医学部附属病院へ。膝を専門に外来や手術など臨床経験を重ねた。「診断が難しい分野で、やってみようと思った」。実際、診療所の患者は足腰の痛い人、糖尿病などの慢性疾患の人が目立つという。「内科的な慢性疾患を持つ人は、どこか足腰の疾患があることが多いですね」。
心にしみた「間違ってもいいじゃないか」

「行ってみないか」と声をかけられ洞戸診療所に赴任した。県内に9カ所あった無医の診療所のひとつだった。一番のプレッシャーは、歯科を除く診療科の、さまざまな症状の患者を一人で診ることだった。赴任前には自主的に、名古屋市内の総合病院で内科や外科、小児科の研修もしたという。
着任後、村の人からふと、声を掛けられた。「先生、少しくらい、間違ってもいいんじゃないか」。今でも涙が出そうになる思い出だ。緊張しまくっていた自分を、温かく見守ってくれている人がいた。ゆったりした気持ちで仕事ができるようになった。こうした体験が「診療の要は、人と人とのつながりを確認すること」という信念の根底にあるようだ。
訪問診療や時間外の往診の負担も並大抵ではなかった。昔は深夜でも休日でも電話が鳴った。診療後の夕方に加え、朝も出掛けた。多い月で20軒以上。ときには25キロ以上先の患者宅を往復し、「一晩にぜんそくの子供さんを2人診たこともあった」。
厳寒期は雪に苦しめられた。「北部の板取地区(旧板取村)は、雪の深さが格段に違う」。真夜中の往診後、タイヤが雪に埋まって、近隣の人たちの手助けを受けた。歩いて側溝にはまって脱臼し、肩を固定して診療を続けた。同級生から贈られたヘッドライトが欠かせなくなった。雪道でスリップし、数メートルを転落したこともあったという。

「最期は自宅で」という望みを尊重し、看取りも続けた。傍で見守り続けることもあれば、判断次第では「様子を見ていてください」と一旦帰宅することもあった。翌朝に再訪すると、布団の上に小刀があった。「何軒も往診した後でヘトヘトだった。『朝まで待ってもらえるか』と思ったが、失敗だった。申し訳ないことをした」と述懐する。
赴任時に決意した「何かあれば、できる、できないではなく、可能な限り、いつでも出かける」を忠実に守ってきた。「今は働き方改革で難しいかもしれないが、間違えていなかったと思う」という。
これからも「真心を尽くしたい」
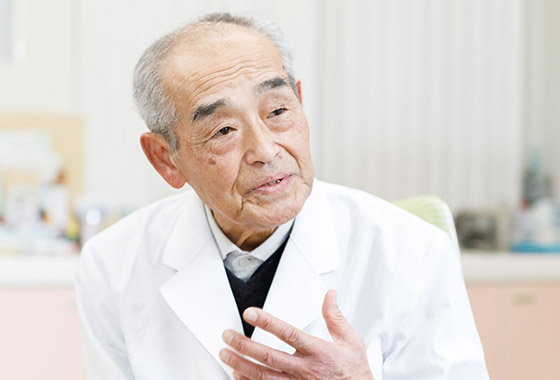
交流にも力を入れた。膝の悪い女性が「私、先生に治療してもらっているときよりも、歌っているときのほうが痛みはないの」と言うので、「それならお手伝いをしましょう」と、「カラオケまつり」を開催し、長く続けた。「人前で歌うと気が張るし、精神状況によい影響がある。一生懸命に肺を使って息を出すのもいい」。体に負担がかからず、痛くないと知り、「操体法」を診療に取り入れた。理学療法士がいないので、リハビリを施せない患者を考えてのことだった。
近年は人口が赴任時の約6割に減り、時間外の呼び出しも少なくなった。だが、一番の理由は「平成19年にぼくが胃の腫瘍で手術したことでは」と思っている。術後の療養中、90歳近い女性が「先生、わしらが使いすぎたんや。だから手術したんや」と言ってくれた。
令和5年春、後任の所長とバトンタッチ。今も支援医師として診療を続けている。「地域の皆さんの温かさ、優秀なスタッフに助けてもらった。本当に運がよかった。熱意だけではできなかった」と感謝を強調する。「一番の目標は『真心を尽くす』。自分の欲と反対の方向だから」という。若い医師にも「寝食を忘れるくらいの気持ちで勉強してほしい」とアドバイスする。
「病み、いずれ亡くなるのは自分も患者さんも一緒。助け合い、慰め合っていこうじゃないか、という『同行医療』の気持ちでやっていきたい」。しっかりと溶け込んだ地域で初志を貫徹する。(中川真)
- 安福 嘉則 やすふく・よしのり
- 関市国民健康保険洞戸診療所医師。昭和22年、岐阜県大垣市生まれ。76歳。岐阜大学医学部卒業。同県立多治見病院、岐阜大学医学部附属病院を経て、57年~令和4年の41年間、洞戸診療所の所長を務める。学校医として不登校の相談や地域の食生活改善にも取り組み、現在も支援医師として診療を続ける。