第13回
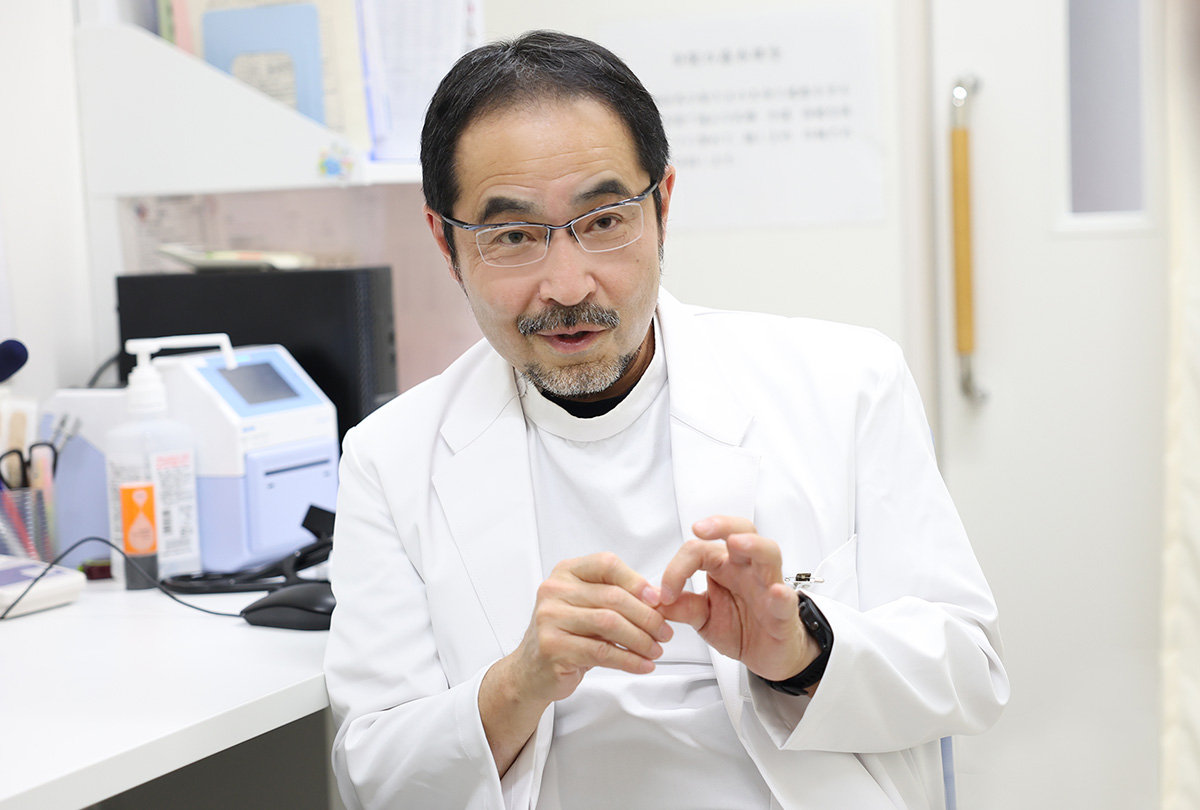
雄大な太平洋に面する「枯木灘」と呼ばれる海岸が続き、背後には「よみがえりの地」とされてきた熊野の山地が迫る和歌山県の南西部のすさみ町。約20年にわたって地域住民の医療に携わってきた。広く住民に予防医療の必要性を伝え理解を求めながら、住民や行政などとともに歩んできた。
赤ひげ大賞の受賞について「行政や病院スタッフに助けてもらい、何より町民のみなさんの協力があってできたこと。町全体の取り組みが評価されたことがうれしい」とほほえむ。
出身は県北部の海南市。活発な子供で、「外傷が絶えなかった」と笑う。公園のすべり台から落ちて、丸一日意識を失ったこともある。これらの体験が医師を目指すきっかけになったという。
同県立医科大学では心臓血管外科を専攻。経験を積む中で、「外科は、悪いところに直接手を加えることで治療することができる。手術を頑張ることで患者さんが良くなるのは、非常にやりがいを感じていた」と話す。
手術しない理想の外科医

平成4年、国際協力事業団(現・国際協力機構:JICA)でエジプトのカイロ大に派遣され、小児心臓外科の技術指導を行うことになった。そこで目の当たりにしたのは、当時のエジプトには子供が心臓手術を受ける施設がなく、長ければ3年待たなければならない状況だった。
日々の手術や技術指導を続ける中、エジプトの子供たちが死亡する原因は下痢や肺炎の割合が高いことを知った。心臓手術の技術を高めることが必要だと感じる一方、少しでも多くの命を救うためには衛生環境を整えるなどの「予防」の重要性を改めて認識した。
「手術のための技術も勉強も一生懸命してきたが、実際には、予防を行うなどして手術をしないように持っていくことが理想の外科医だと思うようになった」と語る。
その後、民間病院の病院長などを経て、平成18年、国保すさみ病院に赴任した。当時のすさみ町は人口約5千人で、「地域包括ケア」を実践するには理想的な規模とされていた。予防的な取り組みを行い結果を出すことで、一つのモデルをつくることができるのではないかと考えた。
赴任当時、常勤医師は5人で日常診療と当直業務を行っていた。住民らにとっても「わが町の病院」として身近な存在だった。

「病院への敷居が低いことで、仕事が終わった夜間に、住民が不要不急の診察にどんどん来ることがあった。病院の事情が分からず、悪気なく来てしまうような状況だった」
医療資源が限られる中、翌日の昼間の医療の質を落とし、昼間の患者に公平ではなくなってしまうと懸念し、町民への働きかけを始めた。
夜に町内の各集会所を回り、頭痛や腹痛といった症状ごとの自己診断方法などの講座を行い、夜間の不要不急の来院の自粛を呼びかけた。「まじめな話ばかりでは誰も聞いてくれないので、ギャグなんかも入れて印象に残るように工夫した」と話す。
また、町の広報誌に約100回にわたって病気についてのコラムを執筆し、日々の健康を意識してもらった。結果的に4年後には町内の休日・時間外の受診者数は多いときの約60%に減少したという。
「町民の協力に自分たちは非常に助けられた。診察の際にはお礼の声をかけてもらうこともあり、励みになった」
創意工夫の「ドクターカー」

救急医療では、平成21年に、全国で2番目に医師を運ぶための緊急車両「ドクターカー」を導入した。町の海岸線近くを走る国道42号はカーブが多いこともあり、交通事故が多発。車内に閉じ込められる事故が発生した際、現場での処置のために病院の車で向かっても、緊急車両ではないので現場に到着できず、器材を担いで走るなどもどかしい経験もあったという。
こうした経緯から「ドクターカー」を導入。一般車に約24万円をかけて一部改造しただけの車両で、現場で使用するエコーなども新たに買いそろえず、訪問診療で使用するものを活用した。しかし、これまでに約30回出動し、現在も同じ車両が現役で活躍している。「ケチと思われるかもしれないが必要最小限の機能があればいい」と話す。
予防医療としては、肺炎球菌ワクチンの接種を国に先駆けて町独自で行ったことをはじめ、小中学生への喫煙防止教室、保育所から中学校までの校医を務めて一貫した健康管理を実施。これまでの取り組みの結果として、町民の健康寿命が延びるなど一定の成果が出てきた。診療科目に縛られない総合診療や、看取りを含めた在宅医療も行ってきた。
ローカル突き詰めグローバルに

太平洋に面する町では、南海トラフ巨大地震などによる津波への対策が進んでいる。同病院も令和5年11月に高台に移転した。建設にあたっては、災害だけでなくさまざまなことを想定して病院スタッフの意見も取り入れた。
玄関前には大きな庇を設け、多数の負傷者が運ばれてきた場合でもトリアージを行うことができる場所を確保。玄関ロビーの壁の内側には酸素を吸入できる器材を設置し、初期治療に使えるようにした。また、数十年先を見越して、建物内を2つに分離して一方を別の用途に利用できるような構造にしている。
「医師の人生で病院の建設に携わることができる機会はまずない。将来を見据えて多くの考えや思いを込めた」と話す。
同町の人口は約3500人まで減少し、高齢化率も47%を超え、将来の日本の姿を先行しているともいわれる。限られた医療資源の中で効率的な健康づくりが課題となり、町が行ってきた一つ一つの取り組みには他の地域の将来のヒントがあると考える。
「『ローカル』というのはネガティブな雰囲気があるが、突き詰めることで『グローバル』になると思っている。行ってきた町の取り組みの結果を示すことが将来の日本で役立つことにつながれば」と語った。(小泉一敏)
- 高垣 有作 たかがき・ゆうさく
- 国保すさみ病院顧問。昭和33年、和歌山県海南市生まれ。66歳。58年、同県立医大卒。愛媛県喜多医師会病院心臓血管外科部長、中谷病院長などを経て、平成18年1月から国保すさみ病院の副院長となり、20年から16年間、院長を務めた。令和6年4月から現職。