第10回

震災時、目を疑う光景を記録し続けた

岩手県大槌町の市街地を壊滅させた東日本大震災の巨大津波を目の当たりにした。異様に長く強い揺れから30分あまり。港から4500メートルにあった4階建ての自宅兼病院を点検していた妻の美智子さんの「水が見える」の声に屋上まで駆け上がった。趣味のカメラのレンズ越しに見た町は「黒く渦巻く海に沈んでいた」。信じられない光景にシャッターを切り続けた。
震災2年後に自費出版にこぎつけた写真集「大槌の津波~その記録、そして出会った人々~」に23枚が解説付きで納められた。震災当日から3月18日までの体験や出来事を時系列で淡々と綴った記録も添えられ、津波の被災現場を知る貴重な資料として評価も高い。
最初の1枚は家々をなぎ倒し白い煙を上げて迫る巨大津波。時間は「15時21分?」。自宅兼病院前の通りは乾いた状態だが、「15時22分32秒」の4枚目で町は「黒く渦巻く海に沈んでいた」。わずか1、2分で4階建ての自宅兼医院は3階まで浸水。「まさか津波がここまで...」。自費出版はこの記憶の風化を防ごうという強い思いからだった。
何事にも動じず気丈に振る舞う

大学の山岳部時代に冬の北アルプスの縦走経験もある山男である。研修医時代に中国とパキスタン国境のカラコルム山脈にあるガッシャーブルムI峰(標高8068メートル)に挑む長野県山岳協会隊に隊付ドクターで参加した。本来は標高5000メートル台のベースキャンプに待機する役目だが、「6900メートルの最終キャンプまで行きました。だって登りたかったもんで」と話すほど。
吹雪や大雪の悪天候で身動きがとれず何度も雪洞を掘ってビバークした経験の持ち主は未曽有の大災害にも動じなかった。「逆に生きてやると闘志が湧いた」という。震災当日、屋上には家族2人と従業員5人、近所の農協職員8人、町社会福祉協議会職員2人が避難、山男の経験と装備が大いに役立った。
夜になって浸水を免れた4階の自宅に移動。無事だった山道具のヘッドランプの灯りを頼りに、フライパンやガスコンロを駆使して焼き餅やカップ麺を提供。布団や毛布で暖をとり、全員が九死に一生を得られた。当人は「ビバークに比べたら何でもない」と毛布にくるまり廊下のソファで熟睡である。

翌朝、自衛隊ヘリに屋上から救助された。1、2階が流れついたがれきに埋まり、降りられなかったからだ。「さすがに自衛隊を見てこれで助かるという実感が湧いてうれしかった」と振り返る。実は自衛隊に救われるのはこれが2度目だった。高校1年生の時に寝袋持参のヒッチハイクで大阪万博に行く途中、自衛隊の兵員輸送車に拾われたことがあったからだ。
「輸送車の中は両サイドに隊員が座り、真ん中に小銃が置いてあって、『これ7.62ミリのNATO弾ですよね』と尋ねたら、『お前は過激派か』と詰問されて『違います、違います』と誤解を解くのに苦労しました」と苦笑い。漫画の戦争ものの知識だったという。学校の砂場やお寺で夜を明かした若き日の冒険旅行の記憶は今も鮮明だ。
苦しい状況でも、避難者同士で助け合う姿が

自衛隊ヘリで運ばれた避難所の寺野弓道場に救護所を設置、本来の医師の業務が始まった。持ち出せたのは往診鞄だけ。避難所には着の身着のままの住民が詰めかけていた。大槌町内は県立大槌病院始め植田医院を含む6つのすべての医療機関が被災、最優先は傷病者の傷病の緊急度や重症度に応じて治療優先度を決めるトリアージだった。
手始めに妊婦と人工透析患者の有無を確認、避難所生活が難しい高齢者を特別養護老人ホームや老人保健施設などに搬送させた。震災翌日の夕方、2人の人工透析患者に付き添い、自衛隊ヘリに同乗して青森県の三沢基地に飛んだ。当初予定の三沢市立病院は停電で対応が困難な状況だったが、受け入れ可能なのは八戸市の赤十字病院と分かり、無事収容することができた。

その夜は病院の当直室に宿泊。翌早朝、病院内の公衆電話で新潟県に嫁いだ長女や東京の知人らに無事を伝えた。市街地が壊滅した大槌町内からの通信手段がなかったからだ。津波襲来の混乱の中で自らの携帯電話も紛失していた。
震災で寸断された道路をたどり、タクシーで5時間以上かかって避難所に戻った。その目に映ったのは避難者が水汲みや薪運び、食事の準備と役割分担をして助け合う姿だった。町内の避難所となっている県立大槌高校に県立大槌病院の医師、町の対策本部も置かれている中央公民館には3人の民間診療所の医師が活動しているのも心強かった。
しかし、寺野弓道場だけで避難者は約400人、医師は1人である。深刻な薬不足に加え、不自由な避難所生活に体調を崩す被難者も増えた。夜中の子供の発熱やけいれんの発作に対応したり、早朝からは診療、避難所生活に認知症を発症した高齢者への対応などもあり、2、3時間単位でしかまとまった睡眠が取れない日々が続いていた。
地域をみんなで診るという意識
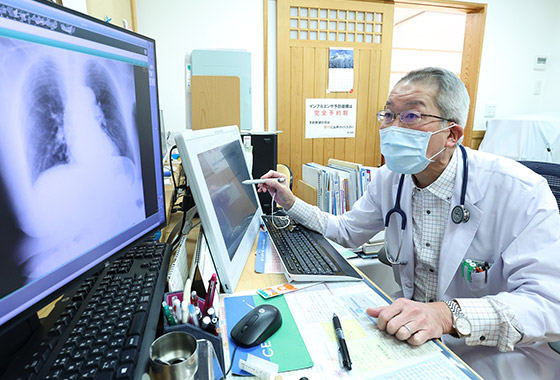
震災数日後にやってきた韓国の医師団が真顔でこう聞いてきたという。「なぜ暴動が起きないんですか」と。避難所の住民が助け合う姿から「あり得ない」と質問をとりあわなかった。3月14日には、釜石保健所から薬品が届き、全国から医療支援も相次ぎ被災地に届きつつあった。
寺野弓道場の救護所にも3月18日から長崎大学医療支援チーム、3月30日からAMDA(旧称:アジア医師連絡協議会・特定非営利活動法人アムダ)チーム、4月18日から大阪JMATチームが参加。5月末に救護所の役割を終えると、6月から県立大槌病院仮設診療所に勤務、7月から寺野弓道場近くに仮設医院を開設、被災地の医療を支え続けた。

自宅兼医院を弓道場近くに再建できたのは震災から5年近く経った平成27年2月。県立大槌病院と連携して地域医療を担う。何事にも自然体で穏やかな人柄。平成14年から地域の医療機関のまとめ役の釜石医師会副会長を務める。「民間診療所と大槌病院の医者もスタッフもすごく仲がいい。地域をみんなで診るという意識がないと地域医療が成り立たないことを知っているから」と話す。町医者の父親に反発していた東京での浪人生活で、都会暮らしは無理と町医者になる決意をして40年あまり。東日本大震災は医師を天職にした。(石田征広)
- 植田 俊郎 うえた・としろう
- 植田医院院長。昭和29年、岩手県大槌町生まれ。67歳(2022年5月12日時点)。金沢医科大学卒。日本医科大学第一内科に入局し東京都立駒込病院循環器科や白十字総合病院内科へ出向。釜石市民病院放射線科長・内科医員を経て植田医院を継承開業した。平成14年から釜石医師会副会長。