第3回
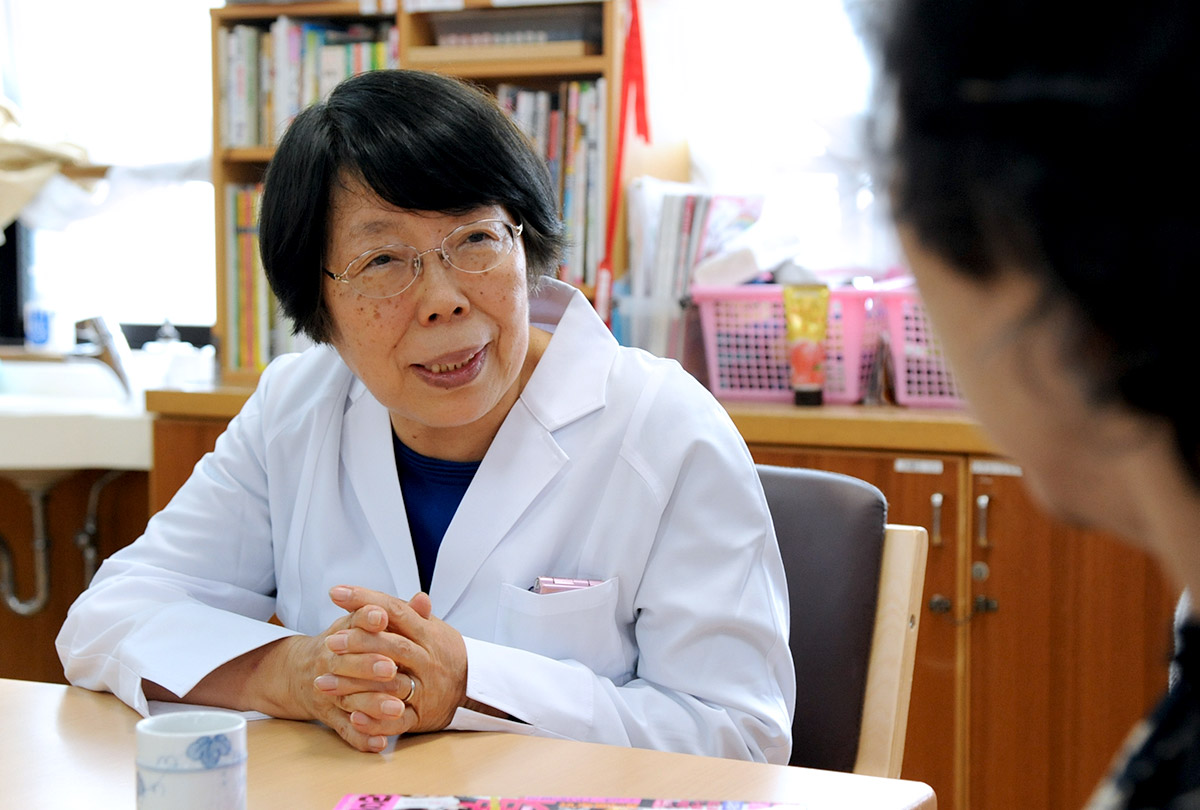


神奈川県横浜市と相模原市に挟まれた東京都町田市成瀬台。戸建て住宅が立ち並ぶ閑静な住宅街の中に、「ケアセンター成瀬」はある。デイサービスや特別養護老人ホームが併設された施設は、地域住民が気軽に立ち寄る交流の場でもある。10月初旬、ここで約40人の住民がこれまでの歩みを振り返る集いを開いた。
「今、この地域は超高齢化社会になった。20年前にボランティア組織ができたのは、当時から高齢化の不安を感じていたからだ」「ボランティアに特別なご褒美はないけれど、一歩踏み出す喜びを覚えた」思い出話に花を咲かせる参加者に、大きくうなずいて応えるのは西嶋公子医師だ。この地域に根差して35年。「医師の前に一住民」として、住民とともに奔走してきた。
高齢者施設に住民が集まる理由は、この施設ができた経緯にあった。実は施設の建設を求めたのも、運営を担ってきたのも、地域の住民なのだ。
「試行錯誤しながらセンターで開催してきた音楽会は50回を超えました」とボランティアの女性。「他の施設ではボランティアを集めるのも大変だと聞いているが、ここにはいつも相談できる仲間がいる。私たちは介護保険を使って来ているわけではないが、介護保険の外なる利用者だ」と男性が気を吐くと、会場は笑いに包まれた。住民の熱気は夜遅くまで途切れることはない。
西嶋医師が「何十年も開業医をやらせてもらって、こんな経験ができた。とてもいい時間を過ごしてきた」と締めくくると、大きな拍手が湧いた。
大病院の限界を痛感

(宮川浩和撮影)

医療と介護の連携─。言うのはたやすいが、介護保険制度が始まるずっと前から、それを目指して活動してきた例はあまりない。
西嶋医師の原点は、国立小児病院などで小児白血病の治療に携わってきた経験だ。有効な治療法は少なく、携わった100人の子供のうち98人が死亡する時代。せめて最期の時ぐらい、家族と水入らずの時を過ごさせてやりたい。しかし、病院のルールでは親が病棟に泊まり込むのは禁止されていた。大病院でできるケアの限界を感じた。
同じころ実父が認知症となり、入院することになった。その病院では薬の過剰投与や身体拘束が行われていた。ここでも病院のケアに限界を感じるとともに、これは人ごとでなく、これから年を取っていく自分たちの問題だと感じた。
開業した町田市成瀬台は新興住宅地。引っ越してきた住民は当時皆若かったが、いずれ高齢化の波は一気にやってくるだろう。そのときに医療や介護は大丈夫だろうか。「温かい家庭で最期まで自立して過ごしたいというのは多くの人の願いです。では、その願いをかなえるには、どうすればいいかを考え始めたのがスタートでした」
病院の患者やその家族に声をかけ、平成元年にボランティアグループ「暖家(だんけ)の会」が設立された。
「自分ならどんな介護を受けたいか」「専門性を持たない普通の人に何ができるか」の2点。つまり、介護を受ける側、介護する側双方の視点を持つことが活動の柱となった。

思いを形にしようと、一軒家を借りて小規模なデイサービスを始めた。利用者が「日本舞踊が好き」と言えば、名取のスタッフが踊りを披露。看護や介護の資格を持たない主婦でも、いつもより多く食事を作り、独居している男性宅に配った。
地域住民へアンケートも行い、約2千人の回答を得た。「近所にケアセンターができたら利用したいか」という質問には9割が「利用したい」、「運営やケアを提供する側としても参加するか」との問いにも6割が「参加したい」と答えた。手応えを感じた。
ケアセンターの設立を市に求めるとともに、資金集めやさまざまなボランティアでの参加を募った。住民の要望に応える形で8年にケアセンター成瀬が開設された。入所者のかけ布団をパッチワークで作ってもらったり、絵や彫刻が得意な人に作品を寄贈してもらったり、プロの演奏家によるコンサートを開いたり...。各自が得意な分野を生かして関わり続けてきた。
最期まで輝けるように
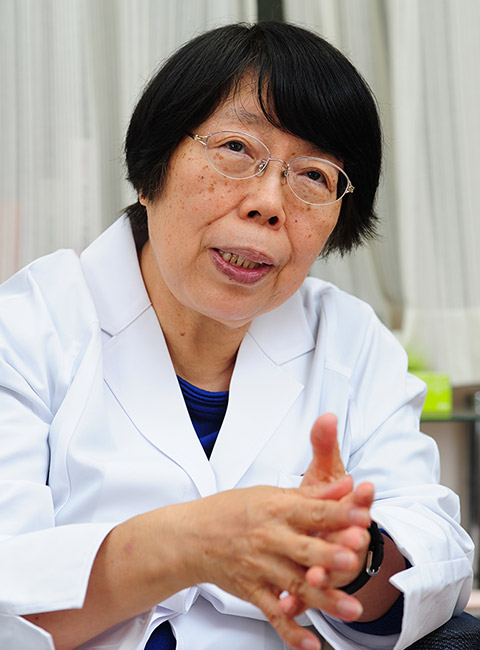
「先生を一言で表現するなら、大活動家!」
センターでボランティア業務を担当する永尾陽子理事はそう評する。
「先生はお医者さんですが、偉ぶらない。同じ住民なんです。住民であることに優劣はないですからね」そんな大活動家は、常に「現場」に突き動かされてきた。国の介護保険制度が始まったときもそうだ。
当時、介護保険を使えたのは65歳以上。どんなに介護を必要としていても、保険料を支払っている40歳~64歳は、パーキンソン病など一部の患者を除いて介護保険を使うことができなかった。
「介護を必要とする末期がん患者が、65歳未満であるだけで介護保険を使えない。64歳のがんと65歳のがんに、どんな違いがあるのか。保険料を納めても、使えずに死んでいけというのか」。厚生労働省への訴えが認められ、18年の制度見直し以降は40歳以上のがん患者も介護保険が使えるようになった。
往診先の患者の娘が言う。「先生にお世話になり始めたころ、『先生に会えて良かった』と言ったら、『それじゃダメ』とおっしゃるんです。どんな医師に当たっても良かったと思えるようにしないといけない、と」。目の前の患者だけでなく、その向こうにいる多くの人のことを考えているからこそ出てくる言葉だ。
難病を患う高齢女性の往診では、一緒に行った旅先で十和田湖(青森県)の湖面が夕日であかね色に染まったことを懐かしく振り返った。「あれはきれいだった」。女性の病気は進行し、もう旅行は難しいが、常に患者の気持ちに寄り添っている。
ケアセンターで一番のお気に入りは、外壁にあるタイル張りの2枚の絵だという。タイトルは「生命の木」。住民がタイル張りを手伝い、「春」「秋」を迎えた木を描いた。
実りの秋を迎えた生命の木に、はたまた沈む前に美しい輝きを見せる夕日に、人生を重ねる。季節は過ぎ、誰もが終末へと向かう。その最期まで輝けるように。その思いが医師を動かし続けている。 (道丸摩耶)
- 西嶋 公子 にしじま・きみこ
- 西嶋医院院長。昭和20年、富山県生まれ。69歳。東京医科歯科大医学部卒。国立小児病院、国立療養所神奈川病院を経て、昭和54年に西嶋医院開設。住民のボランティアグループを結成し、ケアセンターを設立するなど地域医療に尽力している。