第2回

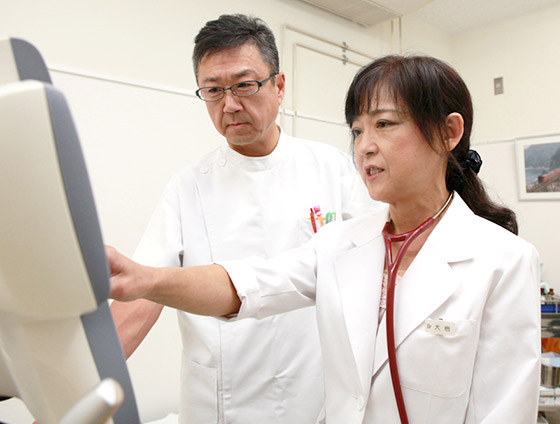
「少しでもお役に立てるのであれば、やってみようかなという軽い気持ちでした。最初は『2年間だけでいい』といわれたんです」
岡山県に隣接する兵庫県上郡町にある大岩診療所院長の大岩香苗医師は、地域住民の健康を守り続けてきた「頼もしき存在」である。
医師になろうと思ったのは小学生の時。外科医だった父親の影響が大きかった。「医院の奥が自宅になっていて、ある日、事故の患者さんが運ばれてきたのを見たのです。痛がる患者さんに処置する父親が格好いいというか、子供ながらにすごいなと思いました」
大学卒業後、病院勤務を経て、実家である相生市の外科病院に戻った。大学の同期だった外科医の敏彦さんと結婚し、子供にも恵まれた。上郡町に開業したのは、そんな昭和63年1月。卒業後6年足らずの若さだった。「大学に戻るつもりで、開業なんて全く考えていなかった」と振り返る。
方針転換したのは父親の意向だ。当時、上郡町には入院施設のある医療機関もなければ、外科医もいなかった。「父が町の方々から『診療所を作ってくれへんか』と要望されて。父は私が暇そうにしているとでも思ったのでしょう。『お前、せえへんか?』となったのです」と笑う。
珍しかった女性の外科医

夫や父の病院のバックアップを受けたが、1人でのスタートだった。「当直医がいるということで『いつ行っても診てくれるらしい』という評判になってしまい、日曜日も平日並みに患者さんが来られる時代がありました」。今では懐かしい思い出だ。
女性の外科医というのは珍しい存在だった。患者からは「女医で大丈夫か?」と露骨に言われたこともある。だが、どこまでもアクティブだ。実家に子供を預けて夫と2人で手術を行うことも珍しくなかった。子供を身ごもった大きなおなかで救急車に同乗し、危篤患者の心臓マッサージをしながら総合病院に向かう経験もした。開業時から中学校の校医も務め、親たちに子供の健康管理のアドバイスを行ってきた。看護専門学校で講師として教壇にも立つ。
最大の理解者である敏彦さんの評価は高い。「僕は手術の時に手をちょこちょこと動かすので、妻から『もっと落ち着いてスパッと』といわれてました。結構、男らしいんです。僕から見ても勉強家だ。取れる資格は取るんだと意気込んでいます。どうも僕に負けるのが嫌なようだ」と敏彦さんは笑顔を見せる。
しかし、その持ち味は女医ならではの気遣いや細やかさにある。それが垣間見えるのが週1回の往診だ。自らハンドルを握り、10軒近くを回る。「おじいちゃんの面倒をよくみてきたよね」「折り紙づくりはまだやっているの?」。診察だけでなく、患者との世間話などコミュニケーションを重視する。そんな香苗医師に対して、高齢患者たちは「先生には親も診てもらいました。なくてはならない存在です」と両手を合わせる。
人付き合いの“達人”

女性患者にとっては、悩みを打ち明けられる貴重な相談相手でもある。「介護をされているお嫁さんが不眠や目まいで来られる。介護疲れや不仲もあったりして、『話を聞いてもらえてスッとした』という人もいる。私が何かできるわけではないが、聞くだけでもいいかなと思っています」
持ち込まれる悩みや相談は医療だけではない。仕事や家庭問題から子育てに至るまで、まさに町民の心の支えだ。敏彦さんが「妻は、地域の人たちの家族関係や悩みなど、とにかくよく知っています」と舌を巻くほどの“人付き合いの達人”でもある。
香苗医師は地域医療のやりがいは「患者との触れ合いや信頼関係です」と語る。「開業当時、私のことを娘や孫のように思ってくれた年代が亡くなり、今はその子供さんを診るようになった。世代が替わっていくのを見ているわけで、『おばあちゃんの時もこうだったね』などと思い出話をすることです」
入院ベッドでは自問自答

2~3年のつもりが、あっという間に歳月が流れた。平成5年にはベッドを19床にまで増やし、夫の敏彦さんも同診療所の専従として働くことになってからは、さらに仕事に励んだ。「大きな病院に劣らない手術ができるようにしよう」。これが2人で確認した診察のモットーだった。正月も夜中もなく手術を行った。
そんな診療所に転機が訪れた。夜中に、近くの国道で発生したトラック同士の事故だった。残念なことに、すでに死亡した状態で運転手が運び込まれてきた。きれいに清拭をしてあげることしかできなかった。
翌日駆けつけた運転手の妻の一言に2人は無力感に襲われることとなる。「『何で主人はこんな小さな診療所におるんですか』といわれたのです。家族にしてみれば当然のことだと思うのですが、もっと大きな病院であればどうにかなったのではないかという期待と後悔があったのでしょうね」。悔しかったが、どうしようもなかった。
ちょうどその頃、専門医制度ができた。しかし、症例が足りずに外科の専門医の資格が取得できなかったこともあって、2人で出した結論は入院患者の受け入れをやめることだった。代わりに、患者の要望が多かった耳鼻科と皮膚科を開設した。平成18年、20年近く守ってきたベッドが静かに消えた。

子供たちが大きくなった今、改めて診療所の行く末を考えるようになった。人口減少と高齢化の波が押し寄せる上郡町が、これからどうなるかにも考慮しなければならない。
気掛かりなのは入院ベッドのことだ。「やめずに有床診療所として持ち続けたほうがよかったのでは」と、いまだに自問自答を繰り返している。
夫との二人三脚で切り盛りしてきた診療所は、いまや地域住民にとって「なくてはならない存在」となった。「2人が健康なうちは、やれるだけのことはやろう」。期待に応えるべく、その目はどこまでも住民の暮らしに向けられている。 (河合雅司)
- 大岩 香苗 おおいわ・かなえ
- 医療法人大誠会大岩診療所院長。昭和33年、兵庫県生まれ。56歳。鳥取大学卒業後、岡山大学医学部第一外科や岡山済生会総合病院、半田外科病院(現・医療法人天馬会半田中央病院)の勤務を経て、63年1月から現職。