第5回


JR京都駅からひと駅の距離と、京都市の都市部にある「大森医院」(同市南区)。院長の大森浩二医師は、往診用のかばんを提げて日々、自転車でまちを駆けている。途中、患者や家族に出会うことも少なくない。「寒うなりましたね」。穏やかな笑顔で声をかけると、「実は父の具合が悪いんです」などと言葉を返してくることもある。
こうした会話で、患者らの状況を知ることができることもあり、医院の近くはなるべく自転車で往診するよう努めている。
地域に医療機関は多いが、医療環境が充足しているとはいえない実態があった。社会問題化している「老老介護」や「認認介護」だけでなく、独居高齢者や末期がん患者ら、すぐ近くの医療機関に満足に通えない人も少なくない。
「都会では近隣とのかかわりが少ない分、周囲の人の目が届かないことも多い。医療のスペシャリストはたくさんいても、そこにたどり着けない人もいる」
高齢化が進む中、往診の需要は増し、多いときで1日に5人ほどの自宅を訪ねている。二十数人いる往診患者のうち約半数が独居高齢者だ。
疾患だけでなく人を診る
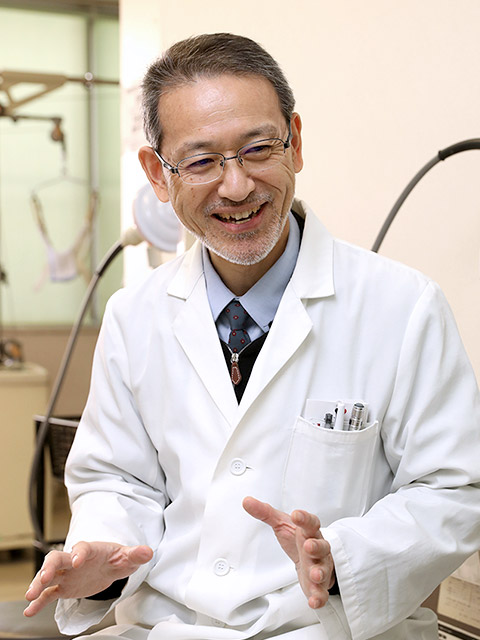
ある金曜日の昼過ぎ、介護ヘルパーのケアを受けながら1人で暮らす女性(89)宅を訪れた。「寒うなりましたけど、大丈夫ですか。夜は寝られますか」「お昼ごはん、今日は何だったん?」。ベッドに座っていた女性と目線を合わせながら、ゆったりとした口調で話しかける。手や指、足と丁寧に一つ一つ触診すると、女性の表情が和らいでいった。
「お肌もつやつややし、達者で生きられますわ」と弾む声で言うと、30年近く年の離れた女性が「親に会ったみたいにほっとしますわ」と笑った。
医院の近くに住むこの女性は最近までタクシーで通院していたが、歩くのが困難となり往診を求めた。こうした都会にある医療の隙間を埋めるべく、地域のかかりつけ医として地道な診療を行っている。
在宅での医療の質を向上させるには、中でも食事が重要と考え、自身が窓口となり都会の“資源”を活用。歯科医や薬剤師、管理栄養士ら多彩な職種と連携して行う「地域包括ケア」をいち早く実践した。

退院後に食事がおろそかになり鬱状態に陥ったが、管理栄養士が自宅を訪れて食事管理をすることで笑顔を取り戻した患者もいる。入れ歯を長年入れたままで食事を満足にとれなくなっていた高齢患者宅には歯科医が訪問。患者自身は食べる喜びを再び味わうことができ、家族からは「きれいな姿で看取ることができた」と感謝を告げられた。
チームとして患者の生活そのものにかかわり、家族ともに心穏やかに過ごすことができるように努めることが、主治医としての役目と考えている。
主治医の熱意が患者を救う
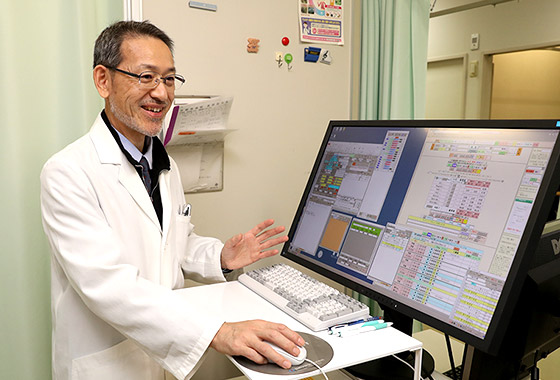

大森医院は昭和30年、外科医だった父親が開業。病院とともに育ち、老若男女問わず地域に住む患者がすぐ身近にいる環境が当たり前だった。物心ついたころから、父の背中を追いかけて医師になる道を選んだ。
父親の代からの患者は高齢になり、子供や孫もかかりつけとなっており、家族全員の健康を預かっている。
約20年前に医院を継ぐまで、大学病院の消化器外科医として第一線で最新の技術を磨いてきた。医師としての歩み方は大きく転換したが、「主治医の熱意が患者を救う」という信条は変わらない。
勤務医時代と異なり、幅広い疾患に対する知識を求められたが、多岐にわたる疾患に総合的・全人的に対処する専門医となるため、「日本プライマリ・ケア連合学会指導医」の資格を取得。地域の潜在力も掘り起こそうと、地元医師会「下京西部医師会」に「プライマリ・ケア教育の会」を設立し、約2年半前から2カ月に一度、30人ほどの医師と勉強会を開いている。
平成23年に発生した東日本大震災では、JMAT(日本医師会災害医療チーム)の京都府医師会の第1陣のリーダーとして福島県会津若松市に赴き、避難者の状態を診て回った。昨年の熊本地震の際も、発生直後に被害の大きかった熊本県益城町を訪問。避難所を訪れて医療ニーズの掘り起こしに努めた。
このとき、医院を守っていたのは医院内で耳鼻咽喉科を診療している医師の妻、敦子さん(57)だ。「普段の診療も被災地の活動も、家族のサポートがないとできない」と感謝の気持ちを忘れない。
目線を合わせて対話

被災地での活動で必要性を改めて認識した一つは、19年から地元医師会で取り組んできた「診療連携カードシステム」だった。患者の疾患名や薬剤アレルギー、使用薬剤名などが閲覧でき、災害時や緊急時でも切れ目のない医療情報の共有化が可能な仕組みで、今後、採用地域を増やしていきたい考えだ。
また、約2年半前からは地元医師会の医師14人で「看取り当番」制度を開始。土・日曜日や祝日に当番を決めて、出張などで医院を離れている際、それぞれの患者の容体が急変しても対応できるようにしている。ただ、これまで一度も出動したことはない。「主治医がみな熱心で、患者の状態が危ないと思うと、出張先からとんぼ返りしたり、どこにも行かなかったりで」とはにかむ。
「先生に看取ってほしい」。患者や家族の信頼を受け、自宅での看取りを希望されることも増えたことは、「医者冥利に尽きる」と言い切る。ただ、患者本人と家族の意思が相反することもあり、ともに尊重しながらの医療の選択は困難を極める場合もある。そうしたとき、自身の父親を自宅で看取ったときの経験が支えになっている。

仕事一筋で、偉大な存在だった父親が肺がんを患い、体は痛く、呼吸さえもつらい状態となり、最期の4カ月ほどは動くこともままならなくなった。「患者さんが親を看取るときの気持ちがよくわかる。自然と寄り添えるようになった」。
患者の訴える言葉や家族の思いに熱心に耳を傾ける。そうして、目線を合わせて“対話”する姿勢から、みなの納得が生まれる。「頼れる慈父のようでありたい」。今日も患者にやわらかな顔で向き合う。(山㟢成葉)
- 大森 浩二 おおもり・こうじ
- 京都市南区の大森医院院長。昭和31年、京都市生まれ。60歳。京都府立医科大医学部卒。同大学付属病院第2外科助手や府立与謝の海病院(現・府立医大付属北部医療センター)外科副医長などを経て、平成8年に大森医院を継承。多職種と連携した在宅医療に取り組み、患者や家族に寄り添う在宅での看取りも実践する。